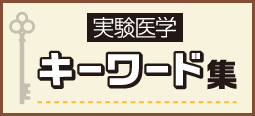概論
神経免疫学―体内の2大ネットワークの連動
Neuroimmunology-two cooperative network systems
井上 誠
Makoto Inoue:Department of Comparative Biosciences, University of Illinois at Urbana-Champaign(イリノイ大学アーバナシャンペイン校)
神経免疫やNeuroimmunologyという言葉を最近よく耳にする,目にするという人もおられるのではないだろうか? 神経免疫は神経系と免疫系の密接な相互作用を紐解く分野であるが,近年,この両者の相互作用解析により,神経変性疾患や免疫性疾患の病態形成機構が明らかとなりつつある.また,私たちが経験的に感じていた「病は気から」の科学的根拠も明らかになってきた.近年,急速に発展している神経免疫分野は,さらに他の分野と融合することでますます発展しうる.本特集が神経免疫分野を広く浸透させ,他の分野との融合のきっかけとなってくれればありがたい.
はじめに
免疫学や神経科学の進歩に伴い,免疫系が神経機能を調節することや神経系が免疫機能を調節することが明らかになってきた.PubMedで,“Neuron”をキーワードに入れると初出は1900年の論文が検索され,“Immunology”を入れると1912年(“Immunity”では1869年) の論文がヒットする.これら研究分野の実に百年以上もの歴史を感じさせられる.これに対して,これらの融合語である“Neuroimmunology”は1982年が最初の論文であり,いかに新しい分野であるかが伺える.しかしながら,神経免疫学(Neuroimmunology)分野の発展と注目度は大きく,2001年に発刊された学術誌Nature review immunologyでは第1巻で神経免疫学に関する論文を紹介し,2009年には各領域で最も影響力をもち,信頼度が高い学術誌であるNeuronとImmunityが同時期に神経免疫学研究の特集を組んでいる.また,昨年2017年にもNature NeuroscienceとNature Immunologyが合同で特集を組んでいる.さらに,Nature review誌(immunology, neuroscience, neurology)を見ただけでも,神経免疫学に関する総説は発刊された2001年から2008年までわずか1報であったのに対し,この10年で実に66報も掲載され,近年の神経免疫学の目覚しい進歩が計り知れる.
1「病は気から」のサイエンス
さて,神経免疫というと「病は気から」という諺で例えられることがよくある.したがって,この分野の人にはありきたりのフレーズかもしれないが,多くの分野で理解しやすい言葉として,あえてこのフレーズを使用させていただきたい.古くから,ポジティブ思考により病気が治癒されたり,逆に,ネガティブ思考や精神的・身体的ストレスを感じると,病気は悪化することは経験的に知られている.実際,楽観主義や期待感は,すべての疾患ではないが,多くの慢性疾患の軽減につながることが報告されている(興味ある方は,1998〜2015年中に報告された楽観主義・期待感と慢性疾患の関連性をまとめた総説を参照していただきたい1)).これらは神経機構が免疫反応を制御することを示唆するものであるが,その科学的根拠は長らく明らかになっていなかった.しかしながら,近年の神経免疫学研究の進歩により,その科学的根拠が明らかになりつつある.本特集では,この科学的根拠にかかわる研究を含め,神経機能による免疫反応制御システムについて,異なる観点から3稿で解説する(上村・村上の稿,鈴木の稿,上野の稿).そして,神経細胞と免疫細胞にはそれぞれに特異的な分子と思われていた情報伝達物質や受容体がともに発現することから,その逆のシグナルも存在する.すなわち,さまざまな神経変性疾患での免疫システムの関与とその作用機構が明らかになってきている.本特集では,免疫機構による中枢神経反応制御システムと,それに対する脳内保護システムについて,3稿分解説している(許・井上の稿,内野の稿,田村・片岡の稿).
2神経機能による免疫反応制御システムとは
全身的な免疫反応の制御機構としては視床下部―下垂体―副腎系を介した糖質コルチコイドホルモンによるものがよく知られている.最近ではわれわれの日常生活や体内動態で大きく影響をうける自律神経である交感神経や副交感神経/迷走神経による局所臓器における免疫反応の制御機構が着目され,その全貌が明らかになりつつある.この局所的な神経免疫相互作用に関する研究の発展に大きな貢献を示している研究として,局所神経刺激が交感神経系を介し,免疫細胞の中枢神経系への侵入口を形成させるという「ゲートウェイ反射」がある.このゲートウェイ反射を誘発する要因として,重力,電気,痛み,そして,ストレスなどが次々と報告された(上村・村上の稿).特に,近年報告されたストレス誘発性ゲートウェイ反射はまさに「病は気から」を説明する科学的根拠の一つであると思われる.また,ストレスや情動による中枢神経の活動変化を全身の臓器に伝える主要経路として自律神経系があるが,そのうち交感神経は免疫反応に重要なリンパ器官へ投射していることから,免疫反応を直接的に制御していると考えられている.この交感神経によるリンパ器官での免疫抑制機構が明らかとなり,ここからも「病は気から」の一端が明らかになった(鈴木の稿).さらに,交感神経活動は概日リズムにより変動するが,この変動に応じてリンパ器官での免疫応答が概日リズム変動することも明らかとなり,われわれの身に備わった病原体感染に対する生態防御システムとして興味深い(鈴木の稿).また脳や脊髄における中枢神経損傷時に感染症にかかりやすいことが知られている.このメカニズムとして,中枢神経損傷に伴う交感神経回路の再編成が過度の交感神経亢進を起こし,その結果,末梢臓器における免疫反応が抑制され,病原体に対する抵抗力が低下することで,感染症の増加をもたらすことがわかってきた(上野の稿).
これらのように,交感神経系は免疫反応制御にかかわる重要なシステムである.今回スペースの都合上紹介できないが,この他にも末梢臓器に分布する迷走神経が神経伝達物質であるアセチルコリンを介して免疫反応の抑制を示すことや,脾臓神経の活性化を介し,ChAT+CD4+T細胞からのアセチルコリンの遊離を促し,自然免疫細胞でのサイトカイン産生反応を抑制することが報告され,自律神経系による免疫反応制御機構が明らかになってきた2)3).一方,報酬に関連する脳の腹側被蓋野のドパミン作動性神経の刺激で,交感神経系を介して末梢免疫細胞による大腸菌感染に対する防御機能の上昇が促されることも報告されている4).このことも,前述した期待感が病状を改善するという「病は気から」を説明する科学的根拠の一つといえよう.また,大腸菌は自然免疫細胞に作用して炎症作用を誘導するとともに,その構成物質であるα-hemolyisnやN-formyl-peptideを介して知覚神経を刺激し,疼痛閾値を変化させることがが近年明らかになった5).その一方,神経刺激により神経終末から遊離されるCGRP,ガラニン,ソマトスタチンなどは自然免疫細胞に作用し,大腸菌による炎症作用を抑制する5).カンジダ属菌もまた知覚神経を活性化しCGRPを遊離する6).このCGRPはCD301b+真皮樹状細胞に作用してIL(インターロイキン)-23を遊離し,IL-23は真皮γδT細胞から抗真菌作用を有するIL-17を遊離する6).これらもまた,神経機能による免疫応答システムの一つである.
3免疫機構による中枢神経反応制御システムと脳内保護システムとは
免疫シグナルによる神経調節機構もさまざまな疾患で明らかになっている.例えば,難治性慢性疼痛を引き起こす神経因性疼痛における免疫シグナルによる末梢ならびに中枢神経機能変調7),アルツハイマー病やパーキンソン病に対する脳内神経炎症の関与と免疫シグナルの機能的役割8)9),神経変性疾患で増減する腸内細菌とその腸内細菌の種類に依存した腸内免疫反応変調が及ぼす中枢神経機能変調10),ならびに中枢神経への病原体感染に対する免疫システムによる神経機能に対する障害機構と防御機構11)などが明らかになってきた.
免疫システムは感染,ストレス,老化,ならびに,性ステロイドホルモンバランスなどにより大きく影響を受ける.したがって,このような状態変化により,免疫システムによる神経機能制御機構も大きく変化する.代表的な神経免疫疾患である多発性硬化症においてもこれらの因子はその病型や薬物感受性等を変化させる(許・井上の稿).また,妊娠期のウイルス感染などは母体の免疫反応亢進により,胎仔において免疫システム変調に伴う脳機能障害が誘発されることが判明し,自閉スペクトラム症の実態が明らかになってきている(内野の稿).そして,脳内免疫担当細胞であるミクログリアは,種々の神経変性疾患や精神疾患において,それらの症状を悪化させる神経炎症誘導に関与する.その一方,近年,第4のグリア細胞といわれるNG2グリア細胞が神経炎症から脳神経を保護する機能を有することが明らかとなり,神経変性疾患や精神疾患に対する新たな治療標的として注目されている(田村・片岡の稿).
おわりに
この限られたスペースで,近年の神経免疫学研究の発展をすべて紹介することは難しい.しかしながら,各稿で最新の話題を多くとり上げているので,ぜひ本特集号全体から,近年の神経免疫学研究の発展を感じとっていただければ,たいへんうれしく思う.そして,多くの分野と神経免疫学が融合し,さらなる神経免疫学研究の発展につながればと思う.
文献
- Schiavon CC, et al:Front Psychol, 7:2022, 2016
- Chavan SS, et al:Immunity, 46:927-942, 2017
- Chavan SS & Tracey KJ:J Immunol, 198:3389-3397, 2017
- Ben-Shaanan TL, et al:Nat Med, 22:940-944, 2016
- Chiu IM, et al:Nature, 501:52-57, 2013
- Kashem SW, et al:Immunity, 42:356-366, 2015
- Calvo M, et al:Lancet Neurol, 11:629-642, 2012
- Lucin KM & Wyss-Coray T:Neuron, 64:110-122, 2009
- Zenaro E, et al:Nat Med, 21:880-886, 2015
- Fung TC, et al:Nat Neurosci, 20:145-155, 2017
- Klein RS & Hunter CA:Immunity, 46:891-909, 2017
著者プロフィール
井上 誠:長崎大学大学院医歯薬学総合研究科において植田弘師教授の下,2000年に博士課程を修了後,UCLA Chris J.Evans博士の下,オピオイド精神疾患を学び,その後,長崎大学にて日本学術振興会研究員,厚生労働省研究員,講師,准教授として神経科学,特に神経因性疼痛やオピオイド依存等における中枢神経の可塑性機構について研究した.’09年,神経科学における免疫の関与に興味を抱き,Duke大学医学部免疫学科に所属し,Mari L. Shinohara博士の下,感染症や自己免疫疾患における自然免疫細胞ならびに獲得免疫細胞機能を研究した.この新たな分野への挑戦の際,小安重夫博士の著書「免疫学はやっぱりおもしろい(羊土社)」を拝読したことで,免疫学に親しみをもち,研究推進に大きく役立ったことをここに付け加えておきたい.’16年,イリノイ大学アーバナシャンペイン校でAssistant Professorとして自身の研究室を立ち上げ,神経と免疫の両観点から,自己免疫疾患,感染症疾患ならびに神経変性疾患の解明に取り組んでいる.