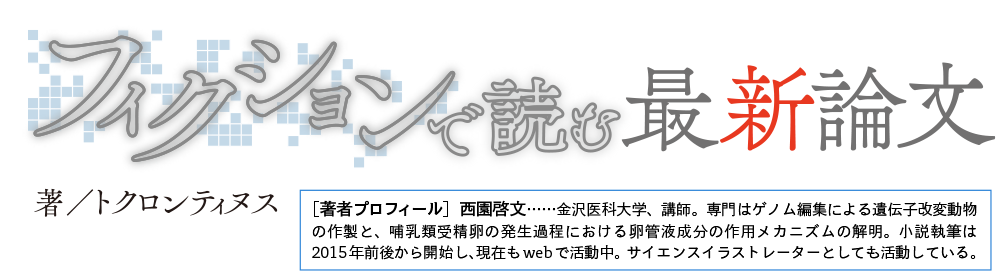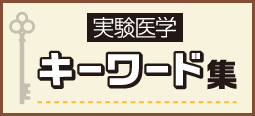第03回『毒をのむ日』
「あ帰って下さい」
「待ってくださいよ! 先生、天城先生!」
大柄でスーツ姿の男が、天城が閉めようとしたドアに革靴を滑り込ませる。
「ちょ、何してんスか、山田さん、警察呼びますよ!」
「いや、だから私が警察ですって!」
そんなこんなの押し問答が十分ほど続き、最後は体力の差であろうか、天城が折れて部屋のなかの安物のソファーに山田が座る。
「……それで、今日は何の用事ですか? 俺もそれなりに忙しいんですよ」
天城が深い溜息と一緒に吐き出す。
「実はちょっと難しい案件でしてね。もう一人お呼びしているのですが」
「修ちゃ……天城先生!」
勢いよくドアを開け、
「もう少し詳しく話聞かせてもらえますか、山田さん?」
しばらくしてから、藤森が山田に尋ねる。
「ええ。事件当日、43歳被害者の男性は今流行のVTuberと言うんですか? 女性キャラクターになりきって動画配信して、結構な人気だったみたいです。事件当日も深夜23時にN市の自宅にて動画生配信をしていたのですが、突然何もしゃべらず、キャラクターも動かなくなったので、配信を見ていた視聴者が関係各所に連絡して、翌々日に鍵のかかったままの自宅にて遺体が発見された、といった状況です」
「死因はわかっているのですか?」
藤森が続けて山田に尋ねる。
「死因は全身の筋肉の麻痺による窒息死。原因は珍しい毒のようなんですがαC-コノトキシンPrXAというイモガイの仲間の毒ではないかということです」
「イモガイ? 京都で、ですか?」
毒を持つイモガイの仲間はもっと南の海に分布していたのではないかと、藤森が驚いて聞き返す。
「調べさせてはいますが、今のところ被害者がどのようにしてこの貝を入手したのかなどはわかっていません。他には変なファンとトラブルになっているだの……ああ、あとは前日に歯科医院にかかっていたってくらいですか」
山田は手帳のメモを見ながら、現状を説明する。
「とにかく、まずはその歯科医さんに話を聞いてみましょうか。ね、天城先生」
藤森のきらきらとしたまっすぐな視線に、天城はもう一度大きな溜息をついてから、しぶしぶ同行を了解するのだった。
「ああ、彼ね。よく覚えていますよ、少し気難しい患者さんだったので」
白衣にマスク姿の林という歯科医師が淡々とした口調で答える。
「気難しい?」
天城が聞き返す。
「とにかく騒ぐ人でね。うちのスタッフたちにも、その動画配信の話しながら度々ちょっかいを出していて、困ったものですよ。唾石症という唾液腺に結石ができる疾患で、定期的にこちらでその除去を行っていました」
なるほど、と藤森が頷く。他に特に変わったことはなさそうで、藤森はそれ以上の会話の糸口を見つけ出せないでいる。
「スタッフさんに聞きましたが、退職されるとか」
山田が会話を少しでも引き延ばそうと、別の話題を振る。
「ええ。カナダへの研究留学が決まったので思い切ってね……それ、何かその事件と関係あるのですか?」
少しきついくらいの冷たい視線を山田に向ける林に、山田は「い、いえ」と言葉を詰まらせる。それをじっと観察していた天城が「ありがとうございました」と立ち上がると、藤森、山田も簡単なお礼を林に伝え、医院を後にする。
「……どうですか、お二人とも」
歯科医院を出て少し経ってから、山田が口を開く。京都のむしむしとした残暑にすっかりまいった様子で、額の汗をポケットのハンカチで拭っている。
「山田さん、被害者のご遺体をもう一度解剖お願いすることはできますか? もし仮にあの先生が除去した結石の影響があるとしたら、唾液腺の周りを調べてみたいと思いまして」
そう藤森が山田に伝える。すると天城は、「それと、もう一つ」と先ほどの林の態度から思いついた疑問点を付け加えた後で、「じゃあ、俺はこれで」とその場を離れるのだった。
「被害者の口腔内から毒素遺伝子の断片が見つかったってことは、何らかの経路でイモガイを入手して口にした……ということになるんですかね?」
一週間が経って、藤森から送られてきたシークエンシングの結果に何とも言えない違和感を覚えていた天城は、山田の電話口の言葉に「はぁ」と生返事で答える。
「あ、そうそう。それと先生に言われて調べていたことですがね、わかりましたよ」
天城が「それで、どうでした?」と聞き返す。
「ええ、林は九州の地方大にいたころはウイルスベクターを使った遺伝子治療という分野の研究室に在籍していたようです。当時は結構な問題児だったみたいで、未承認の動物実験を実施しようとしたんだとか。あとは『嘘が嫌い』と変なところにこだわるタイプで、色々もめごとになったとかまぁ、よくわからん人物ですな」
その山田の報告を聞いた瞬間パズルのピースがはまったように天城のなかで
「なるほど。そういうことか」
天城がそうつぶやくと電話の向こうで山田が「何かわかったんですか?」と焦ったように聞き返す。
「山田さん、あの林って歯科医師をおさえて下さい。彼が海外に
天城は深刻な口調でそう返すと、もう一度注意深く手元の結果を確認した。
「……もぬけの殻、というやつですな」
山田は唇をかみしめると、すぐにどこかに電話をかけ始める。林のアパートには、本人どころか家財道具の一切もなくなっていて、床に散乱している紙ゴミだけが、ここに誰かが住んでいた跡として残っていた。
「ねぇ、修ちゃん。どういうことなの?」
藤森が心配そうに天城を見上げながら言う。
「三雪から送られてきたシークエンスのデータ、確かに毒素本体の32アミノ酸分、つまり96 bpのαC-ココノトキシンPrXAの配列が出ていたでも、少し変わったことがなかったか?」
「変わったこと?」
藤森は思い返すように顎に手を当てて、下を向く。
「開始コドンが無かっただろ? この毒素タンパクはシグナルペプチドの切断とプロセシングを受けて最終的に毒素として機能する。その前半がない」
天城が床に落ちていた紙ゴミを拾いながら言う。
「確かにそうかもしれないけど、それは単に前半部分が読めなかっただけじゃないの?」
藤森の言葉に、天城は一枚の紙きれを手に持ったまま立ち上がり振り返る。
「その代わり、このシークエンスの前半にはP2Aがある」
「P2A!?」
藤森はそれが何を意味するのか理解し、手で口を覆ったまま絶句する。
「最近の論文に毒ヘビの毒腺と哺乳類の唾液腺は共通の構造から派生していて、唾液腺にもメタベノムネットワークと呼ばれる毒の分泌に使われている遺伝子ネットワークが保存されているというものがある。毒腺と唾液腺が似たような分子群を使用しているなら、仮にヒトの唾液腺細胞に発現する分泌タンパクの下流にP2Aでつなげて毒素タンパク質を共発現してしまえば、その毒素はヘビの毒液のように唾液の中に分泌されてしまうどうやったのかはまだわからないが、これはおそらく人為的に導入されたものだよ」
天城の言葉が終わると同時に、恐ろしくなった藤森がへなへなと床に座り込む。
「でも、動機は? 一体なんでこんな恐ろしいことを……」
藤森がうつむきながらそう言うと、天城は手に持っていた紙きれを渡す。
「おそらく、それだろうな」
そこには被害者が演じていた女性キャラクターが印刷されていて、その上からマジックで大きくバツ印がかかれている。
「林は自分の患者として訪れていた被害者が、性別も年齢も違うそのキャラクターを演じて動画配信していたことを知り、以前から持っていた偏執的な正義感を働かせてとも考えられるが、むしろそれは口実で、自分の狂気の発想を試そうとした、が正しいんだろうな。学生時代のエピソードからもその片鱗がみられる」
「修ちゃん、私、怖い……」
弱々しく立ち上がり、自分の胸に倒れこんできた藤森に、天城はそっと肩を抱く。そのまましばらく震える身体を抱きしめて、無言のまま、時間が過ぎるのを待った。それから半年後、海外に逃げていた林が捕まり、その何とも後味の悪い事件は幕を閉じたのだった。
(了)
Barua A & Mikheyev AS:Proc Natl Acad Sci U S A, 118:doi:10.1073/pnas.2021311118, 2021
口腔毒のシステムは有羊膜類で保存されている遺伝子制御ネットワークに由来していることを比較トランスクリプトーム解析で解明した論文。このメタベノムネットワークは、3,000以上のハウスキーピング遺伝子群からなり、ヘビの毒腺と哺乳類の唾液腺で保存されている。医療考証:叢雲くすり(@souyakuchan)
著者プロフィール
- 西園啓文
- 金沢医科大学、講師。専門はゲノム編集による遺伝子改変動物の作製と、哺乳類受精卵の発生過程における卵管液成分の作用メカニズムの解明。小説執筆は2015年前後から開始し、現在もwebで活動中。サイエンスイラストレーターとしても活動している。