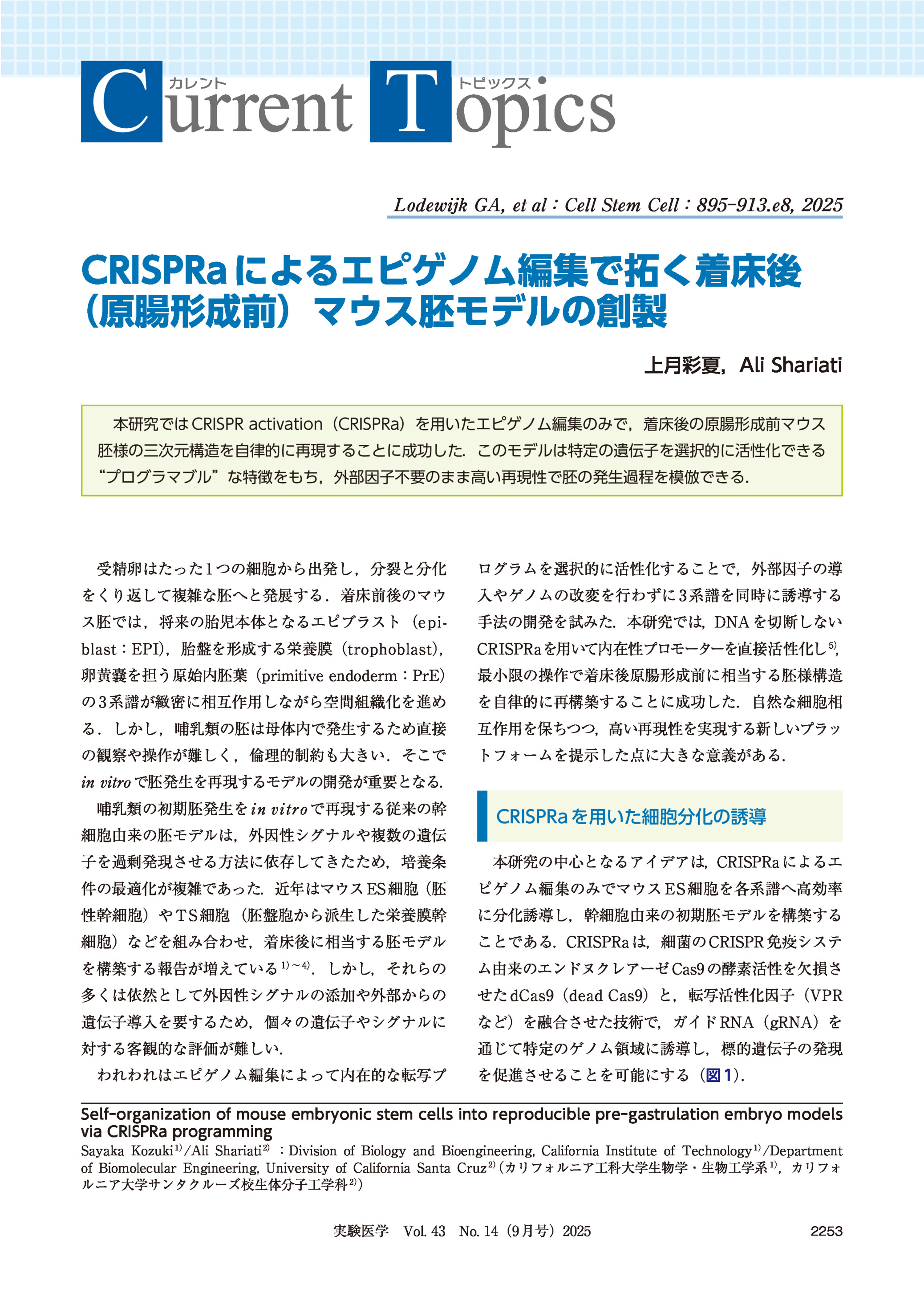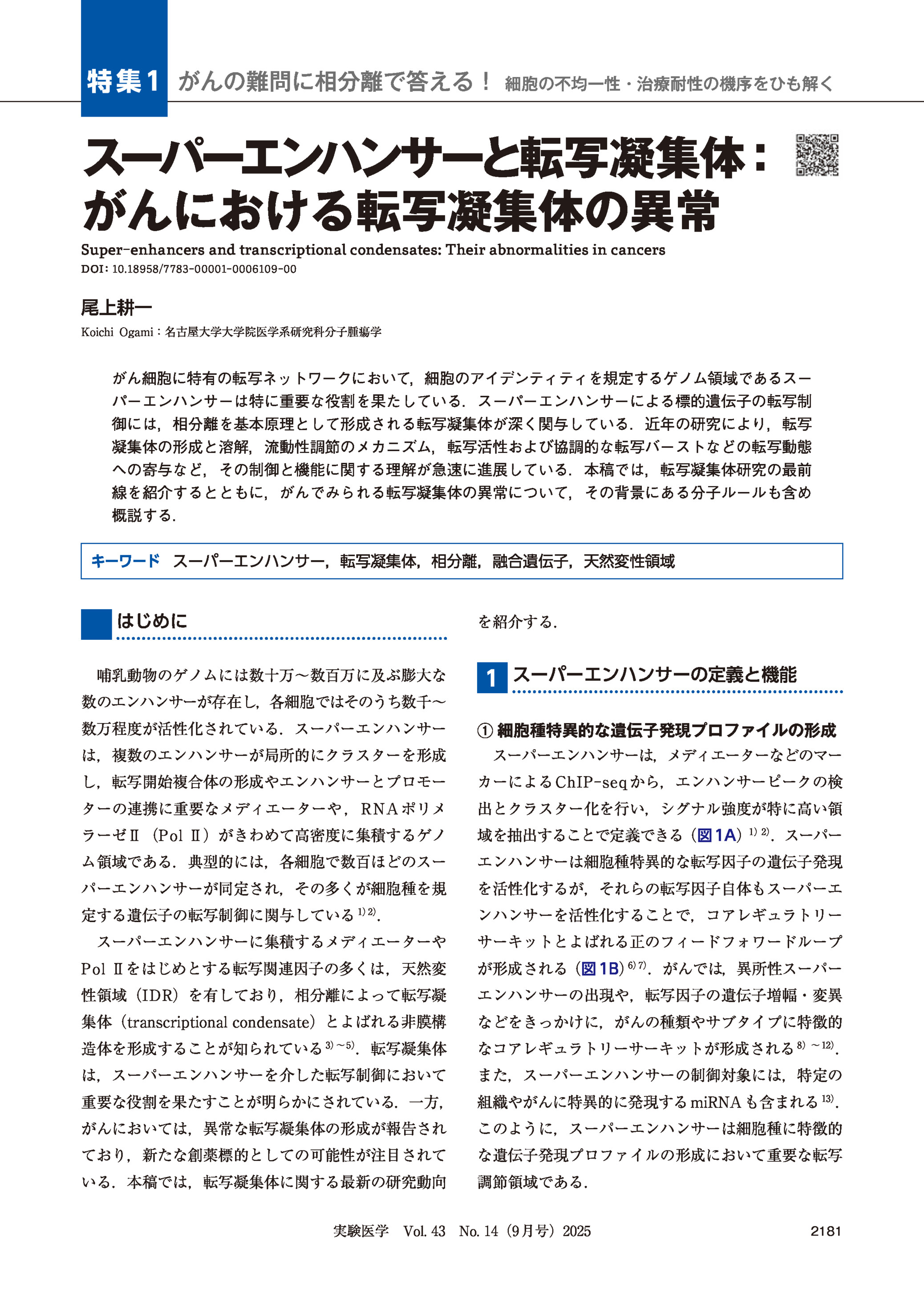私は日々,テーブルで数式を書き,食事をとる.そのため「新しいテーブル買うてん」「どんなん?」といった何気ない会話も自然に成立するし,脚の一本とれたテーブルを見れば,それが「壊れた“テーブル”」であることもすぐにわかる.
しかし「テーブル」とはそもそも何だろうか.おもしろいことに,「テーブル」を定義するのは案外難しい.「平らな天板に四本脚の支柱をもつ物」としても,天板が平らでないもの,脚が三本のものもある.私たちは形式的な定義を超えて,用途や機能,関係性に応じて「テーブル」という語を使い分けている.
この構造は,学問の名前にも一部通じる.私の専門は「数理生物学」だ.「数理モデルで生物現象を解析し,生物学的結論を導く学問」と説明するより,はるかに簡潔だし,分野名は,概念としての専門性やアイデンティティと結びつく機能をもつ.
だが私たちが用いている学問名は,厳密な定義というよりも,便宜的な枠組みに近い.最たる例である「文系・理系」という区分も,歴史的には教育制度上の措置であり,学問的な厳密性は乏しい.それにもかかわらず,この分類は制度や社会意識に深く浸透し,「理系脳」「文系的な考え方」といったレッテルが,思考や教育を固定化し,対立を生んできた.
名付けや分類は便利な一方で,連続的な世界に人工的な境界を引き,事物の対立構造を実体化させる,一種の物象化機能をもつ.そのことが,学問の本質である多様性や包摂性を,知らず知らずのうちに損ねていやしないか,と私は考える.分類は人間の性であるが,興味や関心を出発点に,手法や分野をまたいで問いを立てることで,学問の名・分類・しきたりではなく,関係性の構築を通じて学問に取り組みたいのだ.
これまで私は,移動分散,自家受精,性比,文化進化,生物共存,植物の社会行動,多様性の変動など,幅広い現象をさまざまな数学で研究してきた.その原動力は,「おもしろい現象を,大好きな数学で理解したい」という純粋な興味にある.それに加えてもう一つの動機は,後進の関心の多様さに応答したいという思いである.
私にとって,学生とともに学び,興味を育て,問いを立てていくことは,研究指導の本質だ.一人ひとりの関心に向き合う包摂的な姿勢は欠かせない.これまでに指導してきた学生やポスドクは多くないが,テーマを与え,実行を指示するようなタスク化は避け,できるだけ本人の関心に沿って取り組んでもらってきた(つもりである).数学を使って生物現象を理解するという共通理念のもと,寄生蜂の生活史,アブラムシに寄生するウイルスに“超寄生”するRNA分子,植物の共存進化,温暖化の影響を受けるペンギンの個体群動態……もう,「なんでもこい」である.好奇心旺盛な彼ら彼女らは多くのことを私に教えてくれて,私の興味の幅を力強く押し広げてくれている.
もちろん,学問名は研究費申請や論文査読,教育設計,概念化などに不可欠である.分類の限界を意識しつつ,その社会的機能は理解し,活用すべきだろう.また,共通の名をもつ学術分野に取り組む集団(学会)への帰属性が社会的かかわりを生み出すことも事実だ.だが同時に,学問名は知的営みの本質を必ずしも表すものではないのである.多様な研究対象に取り組むことは,関心や志向の異なる学生との接点を生みやすく,指導における柔軟性や包摂性を確保するうえでも有効といえるのではないだろうか.
参考文献
・「分類思考の世界」(三中信宏/著),講談社(2014)