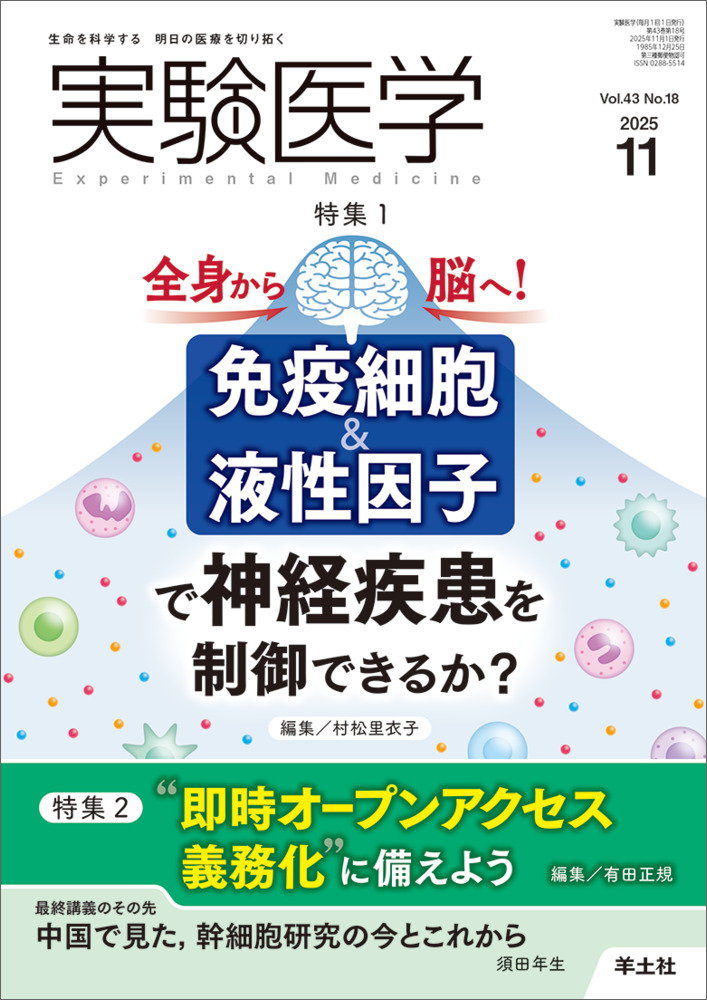話すと広がるという実体験
小学2年生の私ははじめてのポスター発表に臨み,大学の先生方との真剣な議論を経験し,話すと知が増えることを知った.人と話すのが大好きになった原体験だった.小学6年生の初学会発表以来,24歳の今日まで「学会は楽しいところ」という認識は変わらない.
議論を通じて「人とのつながり」も増える.中学生,高校生のとき,研究発表を聞いてくださった大学の先生から共同研究のお誘いをいただいた.研究を〈外〉に出すことを重ねた私は,人間関係と知識の「わらしべ長者」のようなものだった.
研究者だけでなく,さまざまな立場の老若男女とお話しする機会(講演)もいただけるようになり,気がつけば35回を数えていた.意外なことに,それらは「与える」だけでなく「もらう」機会でもあった.私は小学3年生から今日まで「変形菌の自他認識/自己のあり方」の探究を続けているが,自分の研究に社会的な意義があるという気づきを促したのは一般の人々からの反響だった.興味をもってもらえないかもと恐る恐る話した自他認識の話に対して,「いちばんおもしろかった」,「もっと聞きたい」,「発展が楽しみ」,「自己とは何かを考え込んでしまった」,「自己のことをもっと知りたい」という熱い声が返ってくる.世の中の人が「自己」についての知を待っているという確信が,私の研究の方向性をくっきりさせてくれた.
学会発表,論文出版,講演,本の出版,メディアへの出演,そして日常の会話など,それらすべては相手と向き合い伝えるという1つの行い.いつしか私はそう考えるようになった.だから私は研究のことを誰にでも話す.親にも話すし,変形菌なんて聞いたこともない学校の友だちや先生にも話してきた.すると「あいつはヘンケイキンってのが好きなんだって」,「勉強はからっきしだけど,ケンキュウはすごい」と周囲のなかで「自分」が浮き彫りになり,いつしか立ち位置ができる.
研究を自分の内から外に出し続けることが新たな知や人との出会い,居場所,自分の推進力を与えてくれた.
異世界との対話という研究の現場
私たちは,人と人の間をつなぐことができる完全なる言葉をもっていない.
アカデミアのなかでも,分野が違えば使う言葉,基準や信念,めざすこと,何もかもが異なる.放っておいたら話は通じない.でも伝えようとがんばるからこそ,差異ある両者の別の見方が交換される.これが異世界との交流の醍醐味だ.
アカデミアの外にいる人たちにこそ,歩み寄らなければ対話は成立しない.でも,そのなかからキラキラした交歓と交換が得られることもあるのは前述のとおりだ.
異世界への歩み寄りには,日頃の研究ではもたないような鳥瞰的な眼が必要になる.それは自分への理解――例えば,自分が何をわかろうとしているのか――を深めるプロセスでもある.ゆえに私にとって研究を〈外〉に出す経験は,研究を中断して行うというよりも,まぎれもなく「研究の現場」だといえる.いわゆる研究活動と「異世界」との対話の活動は,いつしかどちらを欠いても走れない両輪になっていた.
自分に対話の意思があれば,相手はどこにでもいる.伝えたいという思いがあれば何らかの工夫をして伝え切ることもできる.この実感は,「私たちはまだ,誰にでも何でも通じさせる万能の言葉をもちえていない」ことの再認識でもある.だから誰とでも懸命に対話し続けようという思いがさらに強くなる.私はこれからも,眼前にあるすべての機会で全力を尽くそう.その果てに,真に相手に通じる言葉が生まれることを信じて.